阿息観(あそくかん)と、私の声が帰る場所
静かに息を吐くと、そこに声が生まれていた。
声は、私の命のまんなかから湧いてきた。
それが祈りだと知ったのは、阿息観(あそくかん/阿字観)に出会ってからでした──。
声と共にさまよった日々
歌が好きでした。
自分の声を大切に使って、身体全体で響きを感じながら音を紡ぐのが、ただただ好きでした。
雑に扱いたくない。ちゃんと意識して出したい。
他の音との調和の中でメロディーを奏でることが、何よりも心地よかったのです。
でも、ある時から氣づいてしまいました。
それでは、そのままでは「聞いてもらえない」世界があることに。
刺激が足りない、もっと派手に、もっと音量を…
そんな視線や空氣の中で、私の声が冷たい空間に漂う感覚を覚えるようになっていきました。
動揺すると、恐怖で声を大きくしてしまう私。
何かフックをつけて、聞かせないとダメなんだ、と。
それがプロということなんだ、と。
そんな風に考えるようになっていました。
でも本当は、ずっと違和感がありました。
あの静かに満ちていた時間に、もう一度、還りたかったのです。
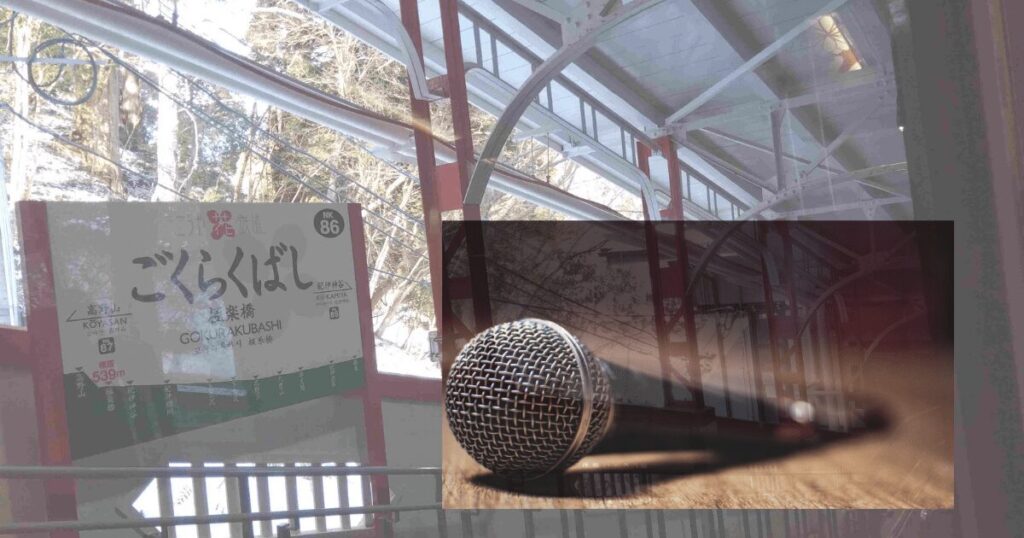
祈りのような声に還るために
私はずっと、道を探していました。
世阿弥の「風姿花伝」を読み、神道の祝詞や仏教の読経をしたり、キリスト教のゴスペルに参加したり──
シャンソン、ジャズ、有名なボイストレーナーさんのレッスンに通ったり…。
けれど、当時は氣づきませんでしたが、私は「自分の声を根本的に変えよう」なんて、これっぽっちも思ってもいなかったのでした。
だって、これが私から。
私の命の響き、自然の声だから。
もし努力で変えた声を褒められても、私はうれしくなかったのです。
そんな私が、ある時出会ったのが、**阿息観(あそくかん)**という声の瞑想でした。
真言密教の根本、「阿(あ)」の音を、自分の身体から、宇宙にまで広げていくように唱える──
それは、単なる発声でもなければ、パフォーマンスでもありませんでした。
まるで、声を出すのは祈りのようなことなのだ──と、
私はそう思いました。
阿息観の実習に通った日々
それから私は、月に1〜2回、阿息観の実習会に通い続けました。
片道1.5時間。雨の日も、寒い日も。
荘厳なお寺の中、参加者と並んで座布団に座り、静かに呼吸を整え、そして声を出しました。
その響きは、自分を包み、やがて空間全体とひとつになるようでした。
誰のためでもなく、競うでもなく、ただ、響く。
その音の中に、私は還っていけたのです。
「声」は「命」そのものでした。
阿息観を通じて出会った方々との時間、
高野山へひとりで訪ねていった日、
東日本大震災のあとの、実施のなかった会にふらっと伺って、
それでも誰かと言葉を交わし、ふっと心が緩んだ日のこと。
全部、いまでも、私の中で息づいています。

いま、私が伝えられること
私は肩書のある専門家でも指導者でもありません。
この声の道や、そこで氣づいたこと、体感したことを体系的に教えるつもりもありません。
でも、私はこの道を、祈りのように歩いてきた。
阿息観に出会ったあの瞬間、私は、自分の声を“命そのもの”として、愛しく感じました。
それは、自分を超えた何かとつながるような、静かなよろこびでした。
言葉がなくても、声は命の響きとして広がるでしょう。
そして、この声は、鳥や虫や木々、自然たちに、もっと自由に届くような氣がするのです。
いま、また声を整えることに立ち返るとしたら、
それは“評価されるため”ではなく、“生きるため”──
命の響きを、もう一度、大事に包みたいから。
その記録として、この文章をここに残します。
そして、
もしあなたの中にも、声に還りたい感覚があったなら、
それは、命がもう一度“静けさ”を思い出そうとしているサインかもしれません。

